
| 触媒としての建築:建築自身は変化せず、それがあることによって周りの 住民の生活や人の関わり方を変化させていく。 |
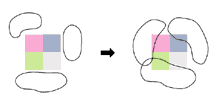 |
| 界面活性剤としての建築;建築を介在させることによって周辺住民の生活や 人の関わり方が変わり、それが変化することによ って建築にまた新たなプログラムをもたらす。 |
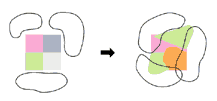 |
せんだいメディアテーク〜UNDER CONSTRUCTION〜

・役所、審査員団、利用者団体、建築家による議論
→設計の段階から、現在まで続く
”建築ができたような気がしない最初からこの建築は使われていた”
←ボランティアによる委員会が自然発生
・すべてが曖昧なまま(全体像が分からないまま)設計が進行
”分かっていることを分かっているようにやるのなら、おもしろい事、新しいことはできない。 手探りでやっていくからおもしろいし、新しい ”
・アドバイザーとしてこれからも関わっていく
・審査員団と利用者団体とのギャップにブリッジを架ける
”公共建築をようやくここまで引きずり込むことができた”
”透明な建築を創りたいというわけではない、境界がないのが理想である”
→コンセプトモデル(初期)で表現
・現実のモノのもつ重み、生々しさ
→軽快な初期スケッチと現実の鉄とのギャップ
”建築-どこかから始まってどこかで終わるというものではない。ひょっ
としたら生きているものではないか?”
”建築は変わり続けるかもしれない。”
・建築家は何かが生まれてくるものをつくらなければいけない
・建築をどこの域まで考えられるのかが問題
”プログラムにまで踏み込まないとつまらない”
”住宅の壁も薄くなっている”
→・情報・モノ(情報に伴う)が影響
・アクティビティの複雑化
→機能だけでは抽出できない
”今までのアーキタイプがなくなっていく”
”境界が失われ、壁というものがなくなっていく”
・新宿は20年前に比べるとはるかに透明度が高い
→情報、アクティビティ
”社会が透明だから建築も透明になっていく”
透明度の高い「社会」から →透明度の高い「空間」へ

■私たちは事前の勉強会で以下の本を読みました。

「透層する建築」伊東豊雄/青土社 2000.10